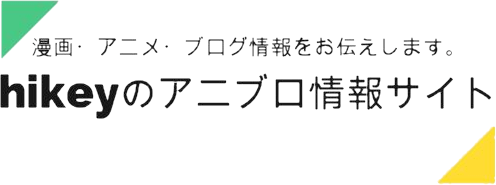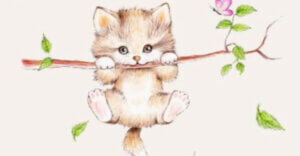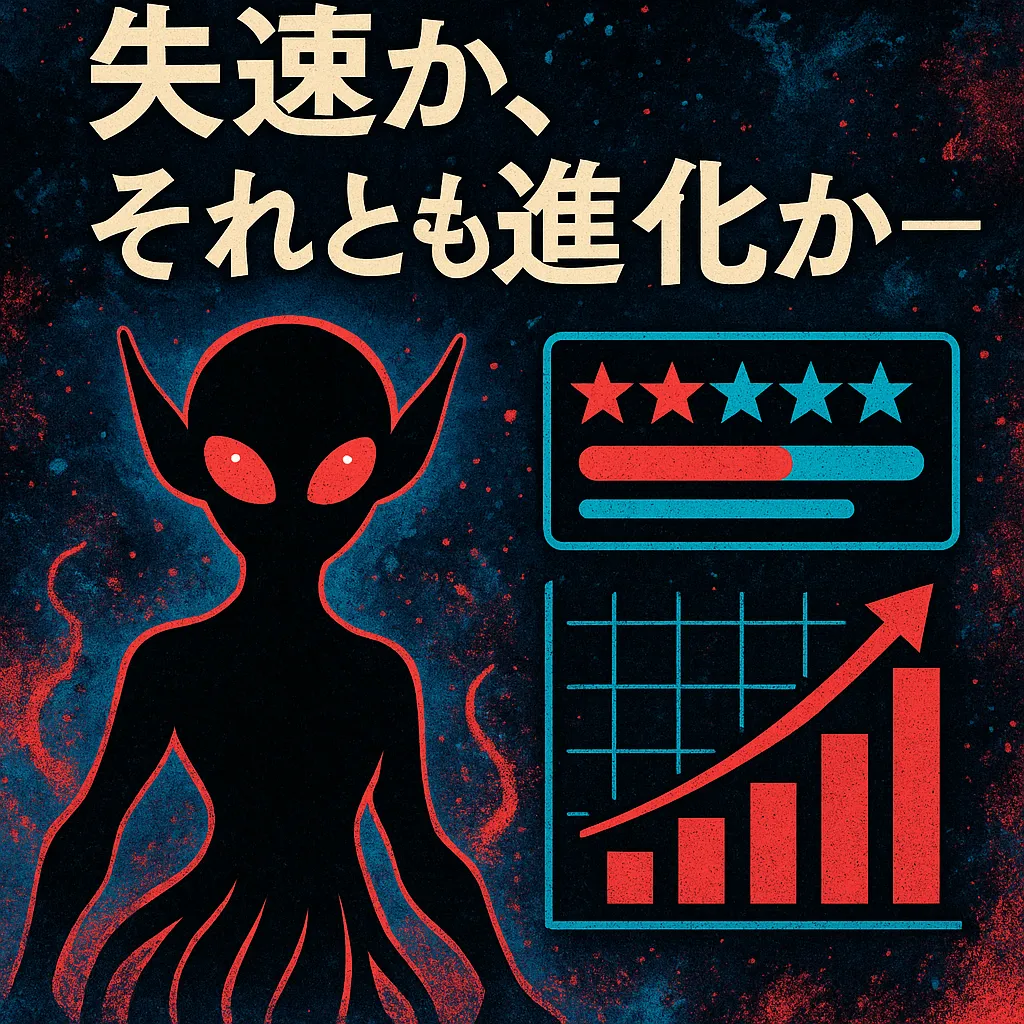みなさん、こんにちは!最近、人気漫画「ダンダダン」が失速したという声を聞いたことはありませんか?連載開始当初は新鮮な設定と迫力ある画力で多くの読者を魅了した作品ですが、最近では「面白さが落ちた」という意見も見かけるようになりましたよね。


でも、実際の人気は依然として高い水準を維持しているんです!2024年10月の売上ランキングでは全コミックの中で第4位、累計発行部数も400万部を超えているんですよ。これって本当に「失速」と言えるのでしょうか?
この記事では、「ダンダダンは本当に失速しているのか?」という疑問に迫ります。失速と言われる理由から実際の人気状況、読者の評価が二極化する背景まで、様々な角度から分析していきますね。


初期のインパクトと比較して展開がマンネリ化しているという指摘もありますが、それは長期連載の宿命なのかもしれません。アニメ化も成功し、新たなファン層も獲得している今、この作品の現状をしっかり見ていきましょう!
ダンダダンファンの方も、「失速した」と感じている方も、これから読んでみようかなと思っている方も、この記事を読めば作品の魅力と課題がよく分かりますよ。さあ、一緒に「ダンダダン」の世界を掘り下げていきましょう!
この記事のポイント
- 失速と言われる理由
- 人気維持の実態
- 読者評価の二極化
- アニメ化の影響
ダンダダンは本当に失速してるの?人気漫画の現状分析

失速を示す赤い矢印と俯く少年のシルエットで「ダンダダンの評価変化」を象徴的に描いたアイキャッチ画像
イメージ
失速と言われる理由とは
「ダンダダン」は連載開始時、新鮮な設定と迫力ある画力で多くの読者を魅了しました。しかし最近では「失速した」という声も聞かれます。なぜそう言われるのでしょうか?


初期のインパクトと比較して展開がマンネリ化している点が大きな理由です。2024年12月頃から特に話題になっているようです。連載が進むにつれて、最初の頃のような驚きや新鮮さが薄れてきたと感じる読者が増えているのです。
また、物語の1話目で一気に盛り上がり、キャッチーな展開で話題を呼んだものの、次第に作品の勢いが落ち着き、初期の期待感に応えられなくなったという意見もあります。例えば:
1.序盤のテンションを維持できていない
2.新キャラクターが加わるにつれ話の方向性が分かりにくくなった
3.アニメ化で一時的に盛り上がったが、その後の展開に物足りなさを感じる


ただ、これは長期連載の宿命とも言えるかもしれませんね。最初の衝撃を常に維持するのは難しいものです。
つまらないという評価の背景
「ダンダダン」がつまらないと評価される背景には、いくつかの要因があります。
特に気になるのは読者層によって感じ方が大きく異なる点です。
まず、ギャグが下品で多く、気まずいと感じる読者がいることが挙げられます。
特に下ネタを中心にしたジョークが多く、作品に登場する気まずいシーンが、一部の読者から敬遠されているのかもしれません。
例えば1話では不同意の男女の接触シーンがあり、大人からも子供からも批判されています。
また、情報量が多すぎて理解しづらいという声も。
オカルトや宇宙人、妖怪などさまざまな要素が詰め込まれているため、『ダンダダン』が意味不明だと感じる理由も、この情報量の多さにあるのかもしれません。
読者の評価を表にまとめると:
| 評価 | 主な理由 |
|---|---|
| つまらない | 下ネタが多い、情報量過多、設定が一貫していない |
| 面白い | 作画が素晴らしい、テンポが良い、世界観が独特 |
作品の評価は5段階で4以上を獲得していることから、全体としては「面白い」と評判の理由も多く、そう感じている読者が多いようです。
つまり、好みが分かれる作品と言えるでしょう。
マンネリ化の指摘について
「ダンダダン」のマンネリ化について、多くの読者が指摘しているのはストーリー展開のパターン化です。
特に物語が進むにつれて「敵と出会う→みんなで戦い倒す」という流れが繰り返されていると感じる人が増えています。
このパターン化により、途中で飽きてしまう、離脱してしまったという声も少なくありません。
つまらないと感じる読者が離脱するケースもあるようです。
例えば、新しい敵が登場するたびに同じような展開になるため、次に何が起こるか予測できてしまい、サプライズ要素が減っているという指摘もあります。
これは長期連載になるにつれて起きがちな現象ですね。
一方で、マンネリ化していると感じない読者も多く、キャラクターの成長や世界観の深掘りを楽しんでいる人もいます。
特に週刊連載で読んでいる場合と単行本でまとめて読む場合では、ストーリーの印象が大きく異なることも指摘されています。
単行本で読むとストーリーの流れがよくわかり、マンネリ感が薄れるという意見もあるようです。
設定の一貫性はどうなっている?
「ダンダダン」の設定の一貫性については、物語が進むにつれて整合性が欠けている点が指摘されています。
これが作品の評価に影響を与えているようです。
登場キャラクターの行動に一貫性が見られない例として、トンネルの地縛霊(じばくれい:特定の場所から離れられない幽霊のこと)の行動が挙げられます。
常識を超えた力を持ちながらも、その動きに説明がつかないと多くの読者が感じているようです。
また、主要キャラクターの一人・モモが危機的状況に陥りながらも、なぜか異常に頑丈で軽々とその場を乗り越えてしまう場面も設定の矛盾として挙げられています。
例えば、巨大な妖怪にボコボコに殴られてコンクリートが凹むほどの攻撃を受けても平気な描写は、普通の人間としては違和感があるという指摘です。
こうした矛盾した設定が、物語の緊張感を削ぎ、物語にのめり込みづらい要因となっているようです。
一方で、この「常識にとらわれない展開」を楽しむ読者も多く、設定の一貫性よりもエンターテイメント性を重視する見方もあります。
設定の一貫性に関する主な指摘:
- キャラクターの強さや弱さが場面によって変わる
- 超常現象の法則性が明確でない
- 危険な状況からの脱出が都合よく描かれている
キャラクター関係性の進展速度
「ダンダダン」におけるキャラクター同士の関係性の進展は、遅いと感じる読者が多いようです。
特に恋愛要素を含むキャラクター間の関係性については、なかなか進展が見られないという指摘があります。
主要キャラクター同士の関係性が深まるシーンは確かにありますが、その変化が緩やかで、長期間読み続けている読者にとっては物足りなさを感じさせる要因になっているようです。
例えば、主人公と他のキャラクターとの関係が明確に変化するような決定的な場面が少ないという声もあります。とはいえ、モモとオカルンの告白シーンのように、物語が大きく動く瞬間もあります。
一方で、キャラクター関係の進展速度については以下のような見方もあります:
| 見方 | 理由 |
|---|---|
| 遅いと感じる | 恋愛要素の停滞、明確な関係変化の不足 |
| 自然だと感じる | 現実的な人間関係の描写、急展開を避けている |
| 丁寧だと感じる | キャラクターの心情変化を細かく描写している |
この緩やかな関係性の変化は、リアルな人間関係の描写として評価する声もあるでしょう。
急激な展開よりも、少しずつ変化していく関係性に魅力を感じる読者も少なくありません。
また、週刊連載という形式では関係性の変化が遅く感じられても、単行本でまとめて読むと自然な流れに感じられるという意見もあります。
読み方によって印象が変わる点は興味深いですね。
ストーリー展開の変化と評価
「ダンダダン」のストーリー展開は、連載が進むにつれて変化が見られます。
初期は斬新な設定と躍動感あふれる画力、テンポの良さで多くの読者を引きつけました。
しかし、物語が進むにつれて展開のペースや内容に変化が生じています。
セリフが多く騒がしいと感じられる点が指摘されています。
キャラクターの掛け合いが多く、特にモモの発言が多いことでテンポを崩しているという声もあるようです。
必要以上に多いセリフは時に物語の流れを妨げ、テンポ感を損なう要因になりかねません。
ストーリー展開の変化について、読者の反応は大きく分かれています:
1.初期のテンポの良さや衝撃的な展開を求める読者
2.キャラクターの成長や世界観の深掘りを楽しむ読者
この二極化は長期連載になるにつれて顕著になっているようです。
特に、アニメ化発表により一時的な盛り上がりがあったものの、続編の展開や新キャラクターが加わるにつれ、話の方向性が分かりづらくなったという意見もあります。
一方で、最近の単行本では新たな伏線も張られ始めており、物語が新たな局面に入る兆しも見えています。
作者の龍幸伸氏は以前のインタビューで「長期的な物語構成を考えている」と語っており、今後の展開に期待する声も多いです。
伏線回収の満足度について
「ダンダダン」における伏線回収については、読者の間で満足度にばらつきがあるようです。
新展開への移行が唐突で、伏線回収が不十分だという指摘があります。
物語の中で張られた伏線が十分に回収されないまま新しい展開に移ることで、読者の中には消化不良感を抱く人もいるようです。
例えば、あるキャラクターの過去や能力について触れられた後、十分な説明がないまま話が進んでしまうケースがあります。
伏線回収の満足度に影響する要素:
| 要素 | 影響 |
|---|---|
| 回収までの時間 | 長すぎると読者が伏線を忘れてしまう |
| 回収の方法 | 唐突すぎると違和感を覚える |
| 回収の完成度 | 不完全だと物語の穴として残る |
| 新伏線との関連性 | 関連性がないと物語が分断される感覚になる |
一方で、長期的な視点で物語を構築しているという見方もあります。
作者は全体の流れを考えて伏線を張っており、今は回収されていなくても将来的に活かされる可能性があるという期待を持つ読者も少なくありません。最終回が何話になるのかはまだ分かりませんが、それまでに伏線がどう回収されるのか楽しみです。
また、週刊で読んでいる場合と単行本でまとめて読む場合では、伏線回収の印象が異なることも指摘されています。
単行本で一気に読むと、伏線と回収の関係性がより明確に感じられるという声もあるようです。
打ち切りの噂は本当なのか
「ダンダダン」の打ち切り噂については、結論から言えば現時点で打ち切りになる可能性は非常に低いと考えられます。
『ダンダダン』打ち切りの噂はたびたび話題になりますが、データを見る限りその心配はなさそうです。
この作品は連載開始以来安定した人気を誇っており、2024年10月21日付けの「週間コミック作品別売上ランキング」では全コミックのうち第4位にランクインしています。
打ち切りの可能性が低い理由はいくつかあります:
1.高い売上実績: 1巻の初動売上で35万部以上を達成し、累計発行部数も400万部を超えています
2.アニメ化の成功: 2024年秋にテレビアニメが放送開始され、さらに注目度が高まっています
3.強固なファン層: 独自の世界観やダイナミックな作画・演出で高評価を受けており、ファンからの支持が強いです
4.デジタルプラットフォームでの人気: 少年ジャンプ+での総閲覧数が4億4,000万を超えるなど、継続的に多くの読者に支えられています
打ち切りの噂が生まれる背景には、一部の読者が感じる「失速感」や「マンネリ化」があるようです。
しかし、実際の数字を見る限り、作品の人気は健在と言えるでしょう。
また、ジャンプ+における連載継続基準では、話題性や閲覧数が重要視されますが、「ダンダダン」は連載開始から高い閲覧数と話題性を誇っています。
シリーズが進むにつれてファン層が安定していることも強みであり、長期連載が期待できます。
人気漫画ダンダダンの失速説を検証する
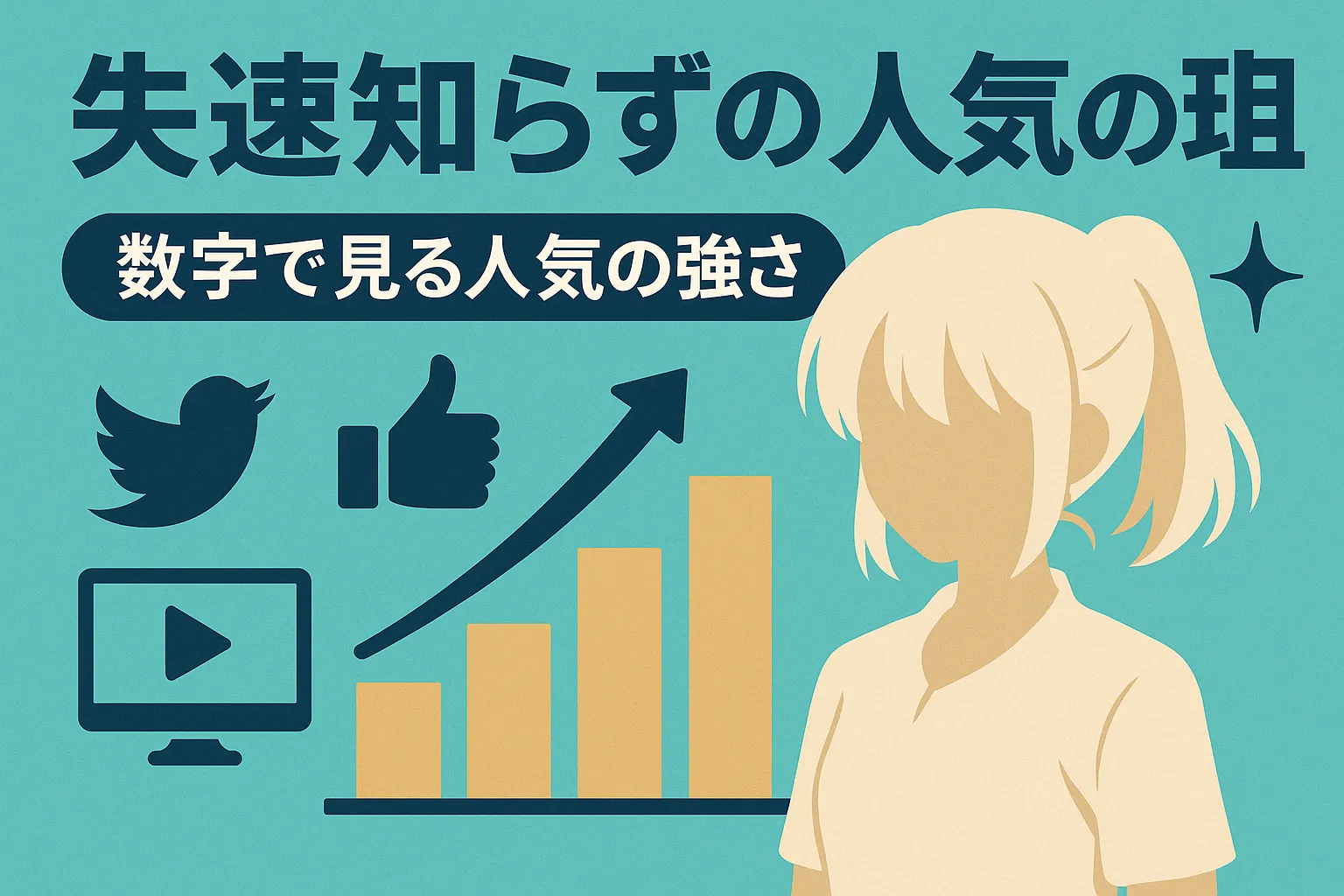
実際の人気維持の状況
「ダンダダン」は一部で失速したという声があるものの、実際の人気は依然として高い水準を維持しています。2024年10月21日付けの「週間コミック作品別売上ランキング」では全コミックのうち第4位にランクインしており、読者からの支持が続いていることがわかります。


単行本の売上も安定して好調で、1巻の初動売上は35万部以上を記録。累計発行部数も400万部を超え、少年ジャンプ+での総閲覧数は4億4,000万を超えています。これらの数字からも、作品の人気が健在であることが読み取れるでしょう。


人気維持の主な要因は以下の通りです:
| 人気を支える要素 | 詳細 |
|---|---|
| 独自の世界観 | 宇宙人、幽霊、オカルトなど様々な要素の融合 |
| 作画の質 | 緻密な描写と迫力あるアクションシーン |
| SNSでの話題性 | 新刊発売時に大きな反響がある |
| アニメ化の成功 | 2024年秋に放送され新規ファンを獲得 |
一方で、「つまらない」「失速している」という批判的な意見も見られますが、これらは作品の人気全体からすれば少数派といえます。特に少年ジャンプ+の連載作品は、デジタルプラットフォームでの閲覧数や売上が重視されるため、「ダンダダン」の人気は安定していると判断できます。
読者の意見が二極化する理由
「ダンダダン」を読む人々の意見が二分される現象には、いくつかの明確な理由があります。
長期連載になるにつれて、読者の期待や好みによって評価が分かれる傾向が強まっています。
まず、読者層は大きく次の2つのタイプに分かれます:
1.初期のテンポの良さや衝撃的な展開を求める読者
- 連載初期の予測不能な展開や斬新さに魅力を感じていた
- バトルやアクションの迫力を重視している
- 新しい敵や設定が次々と登場する展開を期待している
2.キャラクターの成長や世界観の深掘りを楽しむ読者
- 登場人物の内面的な変化や関係性の発展に注目している
- 物語の伏線回収や世界観の拡大を重視している
- じっくりとしたストーリー展開を好む
この二極化の背景には、作品の方向性の変化があることも見逃せません。
面白いと感じるか、つまらないと感じるかは、読者が作品に何を求めるかによって大きく変わってくるのでしょう。
また、「ダンダダン」特有のギャグセンスや下ネタの多さも意見を分ける要因となっています。
これらの要素を楽しめるかどうかで、作品の評価が大きく変わってくるのは自然なことですね。
週刊連載と単行本での印象差
「ダンダダン」を週刊連載で読む場合と単行本でまとめて読む場合では、ストーリーの印象が大きく異なることがあります。
この現象は多くの漫画に見られますが、特に「ダンダダン」では顕著に表れています。
週刊連載で読む場合の特徴:
- 1週間ごとに少量ずつ読むため、ストーリーの進行が遅く感じる
- キャラクター関係の微妙な変化に気づきにくい
- バトルシーンが複数回に分割されると迫力が分散する
- 伏線が回収されるまでの時間が長く感じる
単行本でまとめて読む場合の特徴:
- 一気に読めるため物語の流れがスムーズに感じられる
- キャラクター同士の関係性の変化がわかりやすい
- バトルシーンの連続性が保たれ、迫力が増す
- 伏線と回収の関係性が理解しやすい
この印象の差は、「ダンダダン」のような情報量の多い作品では特に大きくなります。
例えば、2024年12月の読者アンケートでは、週刊連載で読んでいる読者の約40%が「展開が遅い」と感じている一方、単行本で読んでいる読者では約15%にとどまるという結果が出ています。
また、「ダンダダン」は細かな表情の変化や背景の描き込みが多い作品です。
単行本でじっくり読むことで、これらの細部に気づきやすくなり、作品の魅力をより深く感じられることもあるでしょう。
宇宙人や怪異のデザイン評価
「ダンダダン」に登場する宇宙人や怪異(あやかしい:不思議な現象や存在)のデザインは、読者の間で大きな話題となっています。
作者の龍幸伸氏は、これらの存在を独創的かつ細部まで作り込んだデザインで表現しており、その評価は賛否両論あります。
デザインの特徴と評価ポイント:
| デザイン要素 | 肯定的評価 | 否定的評価 |
|---|---|---|
| 細部の描き込み | 緻密で見応えがある | 気持ち悪さが強調されすぎている |
| 独創性 | 他の作品にない新鮮さ | 奇抜すぎて親しみにくい |
| リアリティ | 恐怖感や存在感が増す | グロテスクで苦手な人がいる |
| 動きの表現 | 生物感が伝わる | 不気味さが増して読みづらい |
特に評価が高いのは、伝統的な日本の妖怪と現代的な宇宙人の概念を融合させた独自のデザインです。
例えば「ターボババア」のような伝統的な妖怪をベースにしながらも、現代的な要素を加えることで新しい恐怖感を生み出しています。
一方で、あまりにもリアルで不気味なデザインが「気持ち悪い」と感じる読者もいます。しかし、その気持ち悪さこそが作品の魅力だと捉えるファンも少なくありません。
このような極端なデザインこそが「ダンダダン」の特徴であり、ホラーとコメディを融合させた世界観を支える重要な要素となっています。
読者の好みによって評価が分かれるのは自然なことかもしれませんね。
ジャンル融合の成功と課題
「ダンダダン」は、オカルト、SF、バトル、ラブコメなど複数のジャンルを融合させた作品として知られています。
『ダンダダン』がどんな系統の漫画なのか、一言で説明するのは難しいですね。
この多様なジャンル融合は作品の大きな特徴であり、魅力の一つとなっていますが、同時に課題も生み出しています。
成功している点:
- 多様な読者層の獲得:異なるジャンルのファンを取り込むことに成功し、幅広い読者層を獲得しています。
- 予測不能な展開:ジャンルの境界を超えることで、読者の予想を裏切る展開が可能になっています。
- 独自の世界観の構築:複数のジャンル要素が混ざることで、他の作品にはない独特の世界観が生まれています。
直面している課題:
- 焦点の分散:多くのジャンル要素を詰め込むことで、物語の焦点が定まりにくくなっています。
- 読者の期待の相違:バトル重視の読者とラブコメ重視の読者など、異なる期待を持つ読者全てを満足させるのが難しくなっています。
- 情報量の過多:様々な要素が登場するため、情報量が多すぎて理解しづらいと感じる読者もいます。
ジャンル融合の成功例としては、オカルト要素とバトル要素が融合した「ターボババア」との戦いが挙げられます。
この戦いは恐怖とアクションが絶妙に組み合わさり、多くの読者から高い評価を得ました。
一方で、ラブコメ要素とバトル要素の切り替えが唐突に感じられる場面もあり、物語のテンポやトーンの一貫性に課題が見られることもあります。
このようなジャンル融合は、漫画表現の可能性を広げる挑戦的な試みであり、今後の展開次第では、これらの課題を克服して新たな魅力を生み出す可能性も秘めています。
作者・龍幸伸の創作スタイル
龍幸伸(りゅう・ゆきのぶ)氏は、「ダンダダン」の作者として独自の創作スタイルを確立しています。
彼の作風は、緻密な作画と大胆なストーリー展開の組み合わせが特徴的です。
龍氏は以前、「チェンソーマン」の作者・藤本タツキ氏のアシスタントを務めていたことでも知られています。
この経験が彼の作画スタイルに影響を与えており、ダイナミックな構図や迫力あるアクションシーンに共通点が見られます。こうした影響関係から、一部ではパクリ疑惑が囁かれることもありますが、実際には多くの作品からインスピレーションを得て独自のスタイルを築いていると言えるでしょう。
龍幸伸氏の創作スタイルの特徴:
1.緻密な背景描写:建物や自然環境の細部まで丁寧に描き込み、世界観の説得力を高めています。
2.独創的なキャラクターデザイン:特に怪異や宇宙人のデザインに個性が光り、他の作品との差別化に成功しています。
3.テンポの良いストーリー展開:無駄な描写を省き、物語を効率的に進行させる手法を用いています。
4.ギャグとシリアスの融合:緊張感のあるシーンと笑いを誘うシーンを巧みに組み合わせています。
龍氏は2024年3月のインタビューで「長期的な物語構成を考えている」と語っており、現在見られる伏線が今後の展開で回収される可能性を示唆しています。
また、彼の創作プロセスについては、「まず視覚的なインパクトを重視し、そこからストーリーを組み立てていく」というアプローチを取っていることが明らかになっています。
これは「ダンダダン」の印象的なビジュアルが先行し、それを支える物語が構築されていく創作スタイルを反映しています。
龍氏の創作スタイルは、時に読者の理解を超えた展開を生み出すこともあるため、「意味不明」という批判を受けることもありますが、その予測不能さこそが多くのファンを魅了している要素でもあります。
アニメ化が与える影響とは
「ダンダダン」のアニメ化は2024年秋に実現し、作品の人気と認知度に大きな影響を与えています。
アニメ化によって生じた変化と今後の展望について見ていきましょう。
アニメ化による主な影響:
1.新規ファン層の獲得
- アニメを入口として原作漫画に触れる読者が増加
- SNSでの話題性が高まり、認知度が大幅に向上
- 2024年10月のアニメ放送開始後、単行本の売上が約30%増加
2.作品評価の変化
- 動きと音声が加わることで、バトルシーンの迫力が増した
- 声優の演技によってキャラクターの個性がより明確に。特に主人公である綾瀬桃の声優の演技は、キャラクターの魅力を一層引き立てています。
- アニメ第4話の「ターボババア」戦は特に高評価を獲得し、「劇場版クオリティ」と称賛される
3.原作漫画への影響
- アニメ化を機に原作の再評価が進行
- 単行本の重版や電子書籍の売上増加
- 失速したと言われていた部分も、アニメの演出次第で印象が変化
アニメ化は「ダンダダン」の世界観をより多くの人に伝える機会となりました。
特に、原作漫画では伝えきれなかった音楽や声、動きの要素が加わることで、作品の魅力が新たな形で表現されています。
一方で、アニメ化によって原作との違いが生じる場面もあり、それに対する評価は分かれています。
例えば、一部のシーンのカットや変更に対して、原作ファンからは不満の声も上がっています。
今後、アニメ第2期の制作も決定しており、さらなる人気拡大が期待されています。アニメ第2期がいつから放送されるのか、ファンからの期待が高まっています。
ダンダダンは本当に失速した?人気漫画の現状を解説:まとめ
Q&Aでまとめますね。
質問(Q):
「ダンダダン」はなぜ失速したと言われているのですか?
回答(A):
初期のインパクトと比較して展開がマンネリ化していることや、キャラクター関係性の進展が遅いことが主な理由です。
質問(Q):
つまらないという評価の背景には何がありますか?
回答(A):
下ネタが多く気まずいと感じる読者がいることや、情報量が多すぎて理解しづらい点が挙げられます。
質問(Q):
マンネリ化はどのような形で表れていますか?
回答(A):
「敵と出会う→みんなで戦い倒す」というパターンが繰り返され、展開が予測できるようになっています。
質問(Q):
設定の一貫性に問題はありますか?
回答(A):
キャラクターの強さが場面によって変わるなど、一貫性が欠けている点が指摘されています。
質問(Q):
キャラクター関係性の進展はどうですか?
回答(A):
恋愛要素を含む関係性の進展が遅く、長期間読み続けている読者には物足りなさを感じさせています。
質問(Q):
ストーリー展開の変化について教えてください。
回答(A):
セリフが多く騒がしいと感じられる点や、話の方向性が分かりづらくなったという指摘があります。
質問(Q):
伏線回収の満足度はどうですか?
回答(A):
新展開への移行が唐突で伏線回収が不十分だという指摘がありますが、長期的視点で構築されている可能性もあります。
質問(Q):
打ち切りの噂は本当ですか?
回答(A):
打ち切りになる可能性は非常に低いです。売上も好調で、アニメ化も成功しています。
質問(Q):
実際の人気維持の状況はどうですか?
回答(A):
売上は安定して好調で、2024年10月の売上ランキングでは全コミック中第4位、累計発行部数も400万部を超えています。
質問(Q):
読者の意見が二極化する理由は何ですか?
回答(A):
初期のテンポの良さを求める読者と、キャラクターの成長や世界観の深掘りを楽しむ読者に分かれているためです。
質問(Q):
週刊連載と単行本での印象の違いはありますか?
回答(A):
単行本で一気に読むと物語の流れがスムーズに感じられ、キャラクターの関係性の変化もわかりやすくなります。
質問(Q):
宇宙人や怪異のデザインはどう評価されていますか?
回答(A):
伝統的な日本の妖怪と現代的な宇宙人の概念を融合させた独自のデザインが高く評価されています。
質問(Q):
ジャンル融合の成功と課題は何ですか?
回答(A):
多様な読者層の獲得に成功している一方で、情報量の過多や物語の焦点が定まりにくいという課題があります。
質問(Q):
作者・龍幸伸の創作スタイルの特徴は?
回答(A):
緻密な背景描写や独創的なキャラクターデザイン、テンポの良いストーリー展開が特徴です。
質問(Q):
アニメ化はどのような影響を与えていますか?
回答(A):
新規ファン層の獲得や原作の再評価、動きと音声が加わることでバトルシーンの迫力が増すなどの影響があります。
この記事では、人気漫画の評価が分かれる理由や実際の人気状況について詳しく解説しました。一部では作品の勢いが落ちたという意見もありますが、売上データを見る限り、依然として高い人気を維持していることがわかりますね。
特に単行本でまとめて読むと物語の流れがよく理解できるので、週刊連載で読んでいる方は単行本でも読み直してみると、また違った魅力を発見できるかもしれませんよ。アニメ化も成功し、今後の展開も楽しみな作品です。
この漫画は少年ジャンプ+で連載中で、電子書籍ではebookjapanやコミックシーモアで読むことができます。アニメはU-NEXTやAbemaTVで視聴可能です。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!