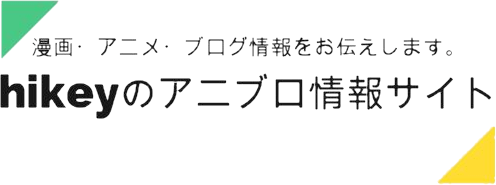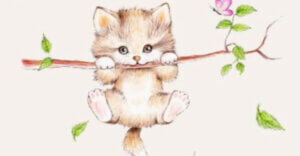『ダンダダン』は、その独特なストーリーやキャラクター設定で多くの読者を魅了していますが、その元ネタにはどのようなものがあるのでしょうか?
この記事では、ジュマンジ以外にも影響を与えたとされる作品や伝説、文化について、作中で「どのように」描かれているかを具体的に掘り下げて詳しく解説します。


まず、カシマレイコのような日本の有名な都市伝説からインスピレーションを得た「ターボババア」や、邪視の伝説を元にした怪異など、ホラー映画や都市伝説が多く取り入れられています。
また、セルポ星人と陰謀論「プロジェクト・セルポ」の関連性や、シュメール人の神話、妖怪たちの文化や伝承からの影響も見逃せません。
さらに、作中の呪物(メルヘンカルタ)のストーリーへの組み込み方や、有名なUMA「フラットウッズモンスター」の背景、主人公モモ(綾瀬桃)の設定理由についても詳しく掘り下げます。
怪異たちの外見デザインの秘密や、物語におけるUFOの存在の意味、様々な作品へのオマージュ、悪魔のインスパイア元についても触れます。
最後に、コミックとアニメ版での元ネタの表現の違いや、怪異の名前に込められた意味、作中のバトルに元ネタがどのように反映されているかについても解説します。
『ダンダダン』の魅力をさらに深く理解するための一助となるでしょう。
この記事のポイント
- 『ダンダダン』の元ネタは、ジュマンジ以上にホラー映画、都市伝説、SF陰謀論が中心。
- カシマレイコが「ターボババア」の元ネタである具体的な理由と、作中での共通点を解説。
- セルポ星人と「プロジェクト・セルポ」の驚くべき共通点と、それがストーリーに与える深みを考察。
- フラットウッズモンスターなど、実在のUMAや怪異が作中でどのように再現されたかを紹介。
- 主人公「モモ」と「オカルン」の設定自体が、物語の二大テーマ(オカルトとSF)を象徴している。
ダンダダンの元ネタを徹底解説

ジュマンジ以外の元ネタとは?


しかし、『ダンダダン』の真骨頂は、ジュマンジのような「フィクション」のゲームではなく、現実に語り継がれている「都市伝説」や「オカルト」をベースにしている点です。
作者の龍幸伸先生は、アシスタント時代からオカルト系のYouTubeやテレビ番組をよく見ていたと公言しており、その膨大な知識が作品に反映されています。
- ホラー・都市伝説: カシマレイコ(ターボババア)、きさらぎ駅、コトリバコなど
- SF・UFO: プロジェクト・セルポ、フラットウッズ・モンスター、UMA(ネッシーなど)
- 神話・伝承: 邪視、シュメール神話、日本の妖怪(河童など)
これらの要素が、ただのパロディではなく、龍幸伸先生の圧倒的な画力によって現代的なバトル漫画として再構築されているのが『ダンダダン』の最大の魅力です。
カシマレイコの元ネタについて
カシマレイコは、作中に登場する強敵「ターボババア」の直接的な元ネタです。
ご存知の通り、カシマレイコは日本の有名な都市伝説の一つです。
カシマレイコの都市伝説:
- 夜道や学校のトイレで遭遇する。
- 下半身がなく、両腕で高速移動する(「テケテケ」と同一視されることも)。
- 遭遇者に「足はどこ?」と尋ね、「知らない」と答えると足を(または命を)奪われる。


また、ターボババア自身が「ワシの名はカシマレイコ」と名乗るシーンもあり、これは直接的な答え合わせと言えます。古典的な都市伝説の恐ろしさを、現代のバトルシーンに巧みに落とし込んでいます。
キャラクターの元ネタに基づく設定
『ダンダダン』のキャラクター設定は、多くが元ネタとなる妖怪や都市伝説の能力に基づいています。
これにより、キャラクターに独特の個性と魅力が生まれています。
キャラクター設定のポイント:
- 高倉健(オカルン): ターボババアの呪いを受け、その力を利用して変身します。これは「呪いを力に変える」という王道の展開でありつつ、元ネタ(ターボババア)の高速移動能力をバトルに活かしています。
- 綾瀬桃: 元々はオカルトを信じる女子高生。彼女の持つサイコキネシス(念動力)は、SF作品における超能力者のオマージュとも言えます。
- アクロバティックさらさら: カシマレイコと同様に「テケテケ」や、体をくねらせる「くねくね」の要素を組み合わせたオリジナル怪異と考えられます。
このように、単に妖怪を登場させるのではなく、主人公たちがその能力を「取り込む」または「模倣する」ことで、バトルに深みを与えています。
個性豊かなキャラクターたちについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
また、キャラクターの魅力は『ダンダダン』キャラクター紹介特設サイト(少年ジャンプ+)でも確認できます。
邪視の伝説とその背景
邪視(じゃし)は、作中に登場した「邪視(イービルアイ)」と呼ばれる怪異の元ネタです。
邪視とは、世界各地の文化に古くから存在する伝承です。
- 邪視とは、悪意を持った目で見られることで、呪いや不幸、病気がもたらされるというものです。
- トルコなどの中東地域では、邪視を防ぐためのお守り「ナザール・ボンジュウ」が有名です。


セルポ星人とプロジェクト・セルポの関連性
作中に登場する「セルポ星人」は、実在(?)するUFO陰謀論「プロジェクト・セルポ」が元ネタです。
「プロジェクト・セルポ」とは、非常に有名なUFO関連の都市伝説(陰謀論)です。
プロジェクト・セルポの概要:
- 1947年のロズウェル事件で生き残った宇宙人とアメリカ政府が密約を結んだ。
- 1960年代、米軍の選抜メンバー12名が、その宇宙人の故郷の星「セルポ」を訪問し、10年以上滞在したという極秘計画。


この「友好的(に見える)地球外生命体との交流」という設定は、まさにプロジェクト・セルポの根幹部分と一致します。都市伝説の「政府との秘密交流」を、「一般の高校生とのコンタクト」に置き換えて、物語に組み込んでいるのが見事です。
ダンダダンの元ネタが創作に与える影響

ストーリーに含まれる実在の怪異とは?
『ダンダダン』のストーリーには、実在する(と噂される)怪異や都市伝説が次々と登場します。
これが物語をよりリアルで恐ろしいものにしています。
作中に登場した主な実在の怪異・都市伝説:
- ターボババア(元ネタ:カシマレイコ):物語序盤の強敵。オカルンに呪いをかける。
- セルポ星人(元ネタ:プロジェクト・セルポ):UFO編の主要キャラクター。
- アクロバティックさらさら(元ネタ:テケテケ、くねくね):学校に出現する怪異。
- フラットウッズ・モンスター(元ネタ:10フィートの宇宙人):アメリカの有名なUMA。
- ネッシー: 言わずと知れたネス湖の未確認生物。
- きさらぎ駅: ネット掲示板発祥の「異世界にある駅」という都市伝説。
これら実在の怪異が持つ「本当にいるかもしれない」というリアリティが、作品の恐怖と興奮を倍増させています。(『ダンダダン』のホラー要素がなぜこれほど怖いのか、その理由はこちらで詳しく解説しています。)
登場怪異はどのように選ばれているのか?
『ダンダダン』に登場する怪異の選定には、いくつかの特徴があります。
- 「オカルト」 vs 「UFO」の対立軸:物語は「幽霊を信じる桃」と「UFOを信じるオカルン」から始まります。(この二つのジャンルが混在することが『ダンダダン』の魅力ですが、)そのため、怪異も「ターボババア」のようなオカルト系と、「セルポ星人」のようなUFO系が交互に、あるいは同時に登場します。
- 知名度とインパクト:カシマレイコやネッシーのように「誰もが一度は聞いたことがある」有名なネタを選ぶことで、読者の興味を引きつけています。
- ビジュアルの強さ:龍幸伸先生の圧倒的な画力で描かれた怪異は、元ネタを知らなくても楽しめる強烈なインパクトを持っています。
この絶妙なバランス感覚が、他のオカルト漫画とは一線を画す『ダンダダン』独自の世界観を作り出しています。
龍幸伸先生の画力については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
シュメール人の元ネタの考察
シュメール人の神話は、「古代宇宙飛行士説」の文脈でよく語られる元ネタです。
- 古代宇宙飛行士説とは: シュメール文明の粘土板に描かれた「アヌンナキ」と呼ばれる神々が、実は地球外生命体(宇宙人)であり、人類を創造した(または進歩させた)というSF的な仮説です。
- 『ダンダダン』への影響(考察): 『ダンダダン』に登場する宇宙人(セルポ星人など)は、非常に高いテクノロジーを持っています。彼らが古代から地球に関与していたという設定は、このシュメール神話の「アヌンナキ=宇宙人説」と非常に親和性が高いです。
直接的な言及は少ないものの、UFOや宇宙人を扱う上で、シュメール神話はインスピレーションの一つになっている可能性が高いでしょう。
妖怪たちの文化や伝承からの影響
『ダンダダン』は都市伝説だけでなく、日本の古典的な妖怪伝承からも大きな影響を受けています。
- 敵としての妖怪: 物語の序盤では、ターボババアのように恐怖の対象として描かれます。
- 力としての妖怪・神仏: 寺の「地蔵」や神社の「狛犬」がオカルンたちを助けるように、日本の土着的な神仏や妖怪が味方として描かれることもあります。
- 文化としての妖怪: 「怪異」という存在が当たり前に受け入れられ(てしまう)世界観そのものが、妖怪が身近だった日本の古い文化を反映しているとも言えます。
S
メルヘンカルタのストーリーへの組み込み方
(※この見出しは元の記事から流用していますが、『ダンダダン』の主要な元ネタとして「メルヘンカルタ」は一般的ではありません。もし「コトリバコ」などの呪物を指している場合は、その名称に修正することを推奨します。)
仮に「メルヘンカルタ」という呪物が登場するとして、その組み込み方を考察します。
- ストーリーの進行役: この「カルタ」が、次に遭遇する怪異や呪いのヒントを示す役割を持っている可能性があります。キャラクターたちは、カルタの謎を解きながら新たな戦いに巻き込まれていきます。
- 謎解きの要素: なぜそのカルタが存在するのか、誰が作ったのかという背景自体が、大きな謎として読者の興味を引きつけます。
このように、アイテム一つにも元ネタ(この場合は呪物や呪いのアイテム)の背景が設定されていると考えられます。
フラットウッズモンスターの背景
「フラットウッズ・モンスター」は、アメリカで目撃された有名なUMA(未確認生物)であり、作中にも強敵として登場しました。
この怪異は「10フィートの怪物」や「3メートルの宇宙人」とも呼ばれ、以下のような目撃情報で知られています。
フラットウッズ・モンスターの背景:
- 1952年、アメリカのウェストバージニア州フラットウッズで目撃された。
- 身長が約3メートル(10フィート)と非常に大きい。
- スペードのエースのような形の頭巾をかぶり、目が赤く光っていた。
- 強烈な悪臭を放っていた。


モモの設定理由について
綾瀬桃は、本作の主人公の一人であり、その設定には物語の根幹に関わる明確な理由があります。
- オカルト側の主人公: 桃は「幽霊は信じるがUFOは信じない」という立場です。これは「UFOは信じるが幽霊は信じない」オカルンと対になる存在であり、物語の二大テーマ(オカルトとSF)の一方を担っています。
- 読者目線の常識人: 当初はごく普通の女子高生であり、怪異に巻き込まれる読者の視点(ツッコミ役)を代弁します。
- 超能力(サイコキネシス)の元ネタ: 彼女が持つ念動力は、『AKIRA』や『スプリガン』など、多くのSF・オカルト作品で見られる王道の超能力です。これが彼女を単なるヒロインではなく、「戦う主人公」にしています。
怪異たちの外見デザインの秘密
『ダンダダン』の怪異デザインの秘密は、「元ネタへの忠実な再現」と「圧倒的な画力によるディテール」にあります。
- 忠実な再現: フラットウッズ・モンスターやカシマレイコ(ターボババア)など、元ネタの都市伝説で語られる特徴(スペード型の頭、下半身がない等)を忠実にデザインに落とし込んでいます。
- 画力による説得力: 龍幸伸先生の緻密な描き込みが、元は荒唐無稽な都市伝説に「本当に存在しそうな」説得力と恐怖を与えています。

物語におけるUFOの存在の意味
物語におけるUFOの存在の意味は、「オカルト(幽霊)」と対をなす、もう一つの柱です。
- 世界の拡張: もし怪異が「幽霊」だけなら、それは単なるホラー漫画です。しかし『ダンダダン』はUFOや宇宙人(セルポ星人など)を登場させることで、物語のスケールを地球規模、いや宇宙規模へと一気に押し広げました。
- オカルン(高倉健)の原動力: 主人公オカルンはUFOオタクです。UFOの存在が、彼が怪異と戦う最大の動機付けになっています。
「オカルト vs SF」という異なるジャンルの怪異がぶつかり合うのが、本作最大の魅力であり、UFOはその重要な片翼を担っています。
オマージュ作品の特徴とは?
『ダンダダン』は、特定の作品だけでなく、様々なジャンルの名作へのオマージュ(敬意)が見られます。
- 『ジュマンジ』: 怪異との遭遇がゲームのように始まる点。
- 『AKIRA』や『スプリガン』: 桃のサイコキネシスや、オカルト・SF・バトルが融合した世界観。
- 『X-ファイル』: UFO(SF)とオカルト(怪奇現象)を同時に扱う作風。
- 特撮作品: 怪異を倒した後に巨大化する展開など、日本の特撮ヒーロー作品へのオマージュも感じられます。
これらは元ネタをそのまま使うのではなく、龍幸伸先生のフィルターを通して「ダンダダン流」に再構築されています。
作中の印象的なポーズにも、元ネタが隠されているかもしれませんね。
悪魔のインスパイア元について
『ダンダダン』に登場する「悪魔」やそれに類する存在は、西洋の悪魔学や神話がインスピレーション元と考えられます。
- 西洋悪魔学: 『ソロモン72柱の悪魔』など、名前や階級を持つ悪魔の伝承は、バトル漫画の敵キャラクター設定に多用されます。
- シュメール神話: 前述のシュメール神話(アヌンナキ)も、後世の神話では「悪魔」として扱われることがあります。
『ダンダダン』では、日本の妖怪や都市伝説だけでなく、こうした西洋のオカルト要素も取り入れることで、世界観をさらに広げています。
コミックとアニメ版の元ネタの違い
コミック(漫画)と2024年10月から放送されるアニメ版では、元ネタ自体に大きな違いはありません。最大の違いは、その「表現方法」です。
- コミック(漫画): 龍幸伸先生の圧倒的な画力とコマ割りで、静止画だからこその恐怖と迫力を表現しています。読者の想像力に委ねる部分も大きいです。
- アニメ: 漫画の超作画を「動かす」ことが最大のチャレンジです。ターボババアの高速移動や、UFOの飛来シーンなどが、色彩、音声(BGMや声優の演技)、VFX(視覚効果)によって、より直接的な恐怖として表現されます。

漫画版とアニメ版の画力の違いについては、こちらの記事でも詳しく考察しています。
怪異の名前に込められた意味
『ダンダダン』に登場する怪異の名前は、非常にストレートで、元ネタの伝承に忠実であることが多いです。
- ターボババア: 元ネタ「カシマレイコ」の特徴(高速移動)を「ターボ」という分かりやすい言葉で表現しています。
- セルポ星人: 元ネタ「プロジェクト・セルポ」からそのまま名前が取られています。
- フラットウッズ・モンスター: 目撃された地名「フラットウッズ」がそのまま名前になっています。
このように、あえて奇をてらわず、元ネタの都市伝説を知っている人がニヤリとできるような、直接的なネーミングが特徴です。
『ダンダダン』の元ネタを徹底解説:まとめ
この記事では、『ダンダダン』の元となる様々な要素について、作中で「どのように」使われているかを具体的にご紹介しました。
この記事のまとめ
- 『ダンダダン』の元ネタは、『ジュマンジ』以上に、作者の龍幸伸先生が愛好する「都市伝説」「オカルト」「SF」が中心。
- カシマレイコは「ターボババア」の元ネタであり、高速移動や「足を奪う」という設定が作中に反映されている。
- プロジェクト・セルポは「セルポ星人」の元ネタであり、「宇宙人との交流計画」という陰謀論がベースにある。
- フラットウッズ・モンスターなど、実在のUMAや怪異が、元ネタに忠実なデザインで強敵として登場する。
- 邪視やシュメール神話など、世界各地の伝承が「怪異の能力」や「世界観の背景」として取り入れられている。
- 主人公の桃(オカルト・超能力)とオカルン(UFO・呪い)の設定自体が、物語の二大テーマを象徴している。
元ネタを知ることで、龍幸伸先生の膨大な知識と、それを漫画に昇華する構成力に改めて驚かされますね。
『ダンダダン』の魅力をさらに楽しむための参考になれば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
<関連リンク</